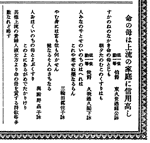|
明治時代 女性応援薬としての命の母
|
|
|
明治時代、女性は家事労働や農作業等に明け暮れ、大家族制の中、体調が悪くてもゆっくり体を休める事もできず、女性特有の病や不快な症状に悩まされる方が多かったようです。 一家の重要な働き手として厳しい生活を強いられる女性のために、「何とか役に立ちたい、病に悩む女性を助け、不快な症状を少しでも軽くしてあげたい」という一心で、省三は研究に没頭し生薬処方の婦人薬を創案しました。
|
クリックすると拡大します
クリックすると拡大します |
|
|